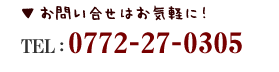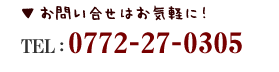「なぜ?ここに越してきたの?」− 世屋高原〈木子村〉へ −
1983年、古都鎌倉から丹後のチベットと言われる木子へ家族6人。末っ子は生まれてまだ9ヶ月。
「なぜ、こんな山奥へ幼い子も連れて来たの?」誰もが疑問に思い、心配した。
鎌倉と言ってもやっぱり都会。一歩外に出ればお金次第で好きなものは買えるし、便利である。
その頃、子ども達を取り囲んでいたのは校内暴力や受験戦争、ゲームセンターにつけっぱなしのテレビ…。
便利さの反面、子ども達の置かれている環境に疑問。父親の帰宅が遅く、家族生活のすれ違い。
「このままではいけない。こんな環境では…」
家族で何度も話し合い、自然豊かなところへ何度も足を運び、
やっと見つけたのが世屋の里、わずか6軒の木子村。
「田舎」のない私たちにとって、初めての田舎である。
山奥では、電波の乱れでテレビのない生活。あるのはただ自然だけ。
不思議なことに、子どもは田舎暮らしに全く抵抗がなかった。
タヌキやキツネ、キジにアナグマ。モリアオガエルなどの貴重な生き物やブナ原生林。
初夏の見事な山藤に蛍たち。秋にはため息が出るほどの紅葉。
澄んだ空気でしか見ることのできない星空。全てが本物である。
畑仕事に草刈り、除雪、ニワトリの世話を家族皆で協力。
便利でないけど、生きることを実感。
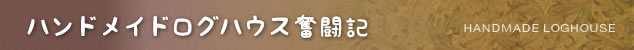
【全てが初めてのログハウス】
鎌倉に暮らしていた時から、家族の使う家具は自らの手で作ってきた。
ここに住むにあたり、夢であったログハウスに家族で挑戦。しかし、家を立てることはもちろん初めて−。
周囲にはログハウスを立てたことのある人もなく、
図書館で「ログハウス」に関する書物を集めてもらい、独学。
設計に関することだけでなく、「道具」についても学んだ。
ログハウスの必需品「チェーンソー」である。
当初、国産メーカーを使用していたが連続運転には向かず、ドイツ製のスティール社に。
また、ログの積み上げに「○○○○○」。
これは丸太の水平・垂直を計る大切な道具。丸太は根元は太く、先になるにつれて細くなる。
これらを組み合わせながら、高さ16mまでブームを持つ大型クレーンを使って積み上げていく。
一日で積み上げられるものはわずかに5本程度。
冬場は積雪が多いため、丸太の積み上げは中断し、皮剥きに専念。春、雪の溶ける頃まで待つことに。
この時期に、室内のシャンデリアやドアノブなど製作。
始めは既成の物も考えたが、やはり合わない。
「ここも自然でないと…」と葉が落ちた頃、山に入り、気に入った形の枝を打ち、ひとつひとつ磨き上げた。納得のいくものが出来た。
他にも、木のぬくもりを感じる丸太のベッドに、ヴァイオリンのボディを型取ったレストルーム台、
お見せすることはめったにないが家族の背丈に合わせて作ったシステムキッチン。
少しずつ積み上がっていく、春が待ち遠しい…。
【丸太は全部で何本??】
設計図から必要な丸太の本数を計算。
一番長いもので12m。短いものは設計図にあわせながらその場で、チェーンソーを使いカット。
建物だけでなく、客室のベッドも丸太。合計すると大よそ986本。
全て皮付きのまま、和知の森林組合(現在:京丹波市)から早朝トラックで運び込まれる。
子ども達は学校から戻ると丸太の皮剥き仕事。
「いつになったら全部終るの?」今になると結構楽しかった思い出に。
一般の住宅と違い、最後まで積み上げて、屋根を載せなければ住むことはできないのがログハウス。
その間、1階の鉄筋コンクリート部分で飯場生活。
夏は窓を開けて寝ていると、顔にカブト虫が飛んでくる。
冬は2mも越す積雪でとても寒く、湯たんぽで足を温めながら家族で過ごした。
この生活こそが家族の団欒。
3度目の春を迎え、ようやく完成。嬉しさが込み上げる。
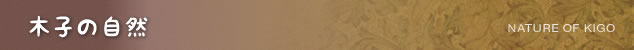
国定公園の指定地域 〜広大な世屋高原ブナ林〜
「幾つも山々が重なり、広大なブナの林。風が渡り、霧が流れる。
谷間からせせらぎの音がのぼってきて、鳥や小動物たちの声がひっきりなしにお喋り。
夜は全天稜線の際まで銀河星雲、途中から枝分かれした天の川に無数の流れ星が生まれ、
蛍たちが飛び交い、淡く光をはなつ。」この地には日本昔ばなしの世界が−。
都会のあらゆる喧騒、その哀しさや苦しみからもまるで異次元のように遥かに、
時が止まったまま、自然の懐に抱かれている。訪れる方々は「街へ戻りたくない」と口々に。
この世屋高原は、日本有数の里山景観が残された僻村の地として、教科書にも紹介。
今は里山景観保全地域として「若狭大江山国定公園の特別指定」となった。
世屋高原の裏山には広大なブナ林が広がって山の匂いを放っている。
かつて日本の山々はこのブナ林に覆われ、基本的な植生として民俗文化を育んできた。
六十歳の樹齢を重ねないと実が付かないブナは、人間の営みに追いつけず、
種が出来る前に切り倒されてきた。
リゾ—ト開発の毒牙からかろうじて逃れることのできた貴重なブナ林。
今やっとその存在価値が認められようとしている。
*下のサムネイルをクリックすると拡大します。
|